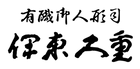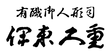御所人形
御所人形は観賞用の人形として江戸時代中期に大成され、宮中の慶事や出産、あるいは結婚など、様々な祝事の際に飾られてきた由緒ある人形です。 その最大の特徴は三頭身であることと、透き通るような白い肌にあります。 江戸時代にはその特徴から「頭大人形」や「三つ割人形」、またその他にも様々な名称で呼ばれていたのですが、当時宮廷や公家、門跡寺院といった高貴な人々の間で愛されたところから明治時代になって「御所人形」という名称で呼ばれるようになりました。 御所人形はその成り立ちや品格から、古くより人形の中でも最も格式高く、最上のものとされています。あどけない稚児の姿をうつしたふくよかな姿、時に愛らしく、時に凛とした表情を見せる気品ある姿、御所人形は日本を代表する人形です。

立雛
その起源は平安時代にまでさかのぼるともいわれる立雛。 伊東家の立雛は御所人形と同じ「桐の木を使用した木彫法」と「日本画の顔料による高盛金彩絵技法」を組み合わせて制作しています。 伊東家では「木彫法」が胴体の十分な強度を保つため、また「高盛金彩絵技法」が京都ならではの雅さを出すための最良の方法と考えています。 衣装部分には「松・藤・撫子」や「鶴亀」など華やかでおめでたい紋様が描かれ、さらにそれを引き立てる品格ある顔立ちが印象的な作品となります。 現在、立雛の制作は当代久重から庄五郎に受け継がれつつあり、その伝承された技によって生み出される作品は、伝統的なものからモダンなものまで多岐にわたり、その魅力は大きな広がりを見せています。

高盛金彩絵
木地の肌へじかに顔料で文様を施した彩絵の筥や台は、奈良時代に作られたものが今日正倉院に数多く伝えられていますが、この伝統はその後宮中に伝わって、木地に胡粉や金銀泥、絵具で優雅な文様を描いた筥や折敷、台などが有職調度として作られ、用いられてきました。 伊東家は、このような有職風な伝統の基盤の上に、近世以降に発達した御所人形の精細な胡粉の技術や人形制作における経験を活かし、桐材を用いた筥や羽子板、小槌などに胡粉の置き上げ彩色を施した高盛金彩絵を制作しています。 胡粉高盛金彩絵は、確かな技術に裏づけられた京都風なあでやかさと気品の高い雅致を備えています。
収蔵先と修復先
皇居
東宮御所
秋篠宮家
常陸宮家
三笠宮家
高円宮家
京都御所
京都迎賓館
京都国立博物館
京都府立京都学・歴彩館
国立歴史民俗博物館
奈良国立文化財研究所飛鳥資料館
斎宮歴史博物館
京都大学国際交流会館
徳川宗家 (徳川記念財団)
一橋徳川家 (茨城県立歴史資料館)
薩摩島津家 (尚古集成館)
加賀前田家 (金沢成巽閣)
肥前松浦家 (松浦資料博物館)
冷泉家時雨亭文庫
京都二条城
姫路城
関門海峡ミュージアム
秦荘町歴史資料館
桐丘学園
小倉学園
鴻池グラナリー
横浜人形の家
大聖寺門跡
宝鏡寺門跡
曇華院門跡
霊鑑寺門跡
林丘寺門跡
法華寺門跡
本山佛光寺
東京本願寺
善光寺大本願
石山寺
鞍馬寺
柳谷楊谷寺
叡山正教坊
大雲院
本性寺
平安神宮
伏見神寶神社
わら天満宮
諏訪懐古神社
祇園祭長刀鉾
祇園祭月鉾
祇園祭函谷鉾
祇園祭南観音山
姥神大神宮渡御祭
松前祭
潮来祭
栃木祭
川越祭
村上大祭
高岡祭
高山祭
名古屋祭
津島祭
八幡祭
大津祭
亀岡祭
天神祭
八尾祭
丹波祭
米国ジョージア州アトランタ市美術館
順不同/敬称略