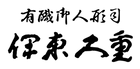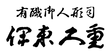伊東家
伊東家は、江戸時代初期、桝屋庄五郎の屋号を代々継承し、現在の京都四条烏丸付近で薬種商を営む家筋でしたが、享保年間、手先が器用で人形作りの才に秀でた当時の当主が人形師として身を立て、御人形細工師を名乗り、病除けの願いを込め子供が薬草を刈る姿をうつした、「草刈童子」を作り、家の守り神といたしました。
その後、江戸時代中期の明和4年(1767)、三代庄五郎が後桜町天皇より宮廷出入りの人形師として「有職御人形司 伊東久重」の名を賜り、これより今日まで当主は代々「久重」を名乗る習いとなっています。
また、寛政2年(1790)には、光格天皇より「入神の作に捺すように」と「十六葉八重表菊紋印」を拝領、以来200年以上の長きにわたり、今日もなお皇室のご慶事に用いられる御所人形を制作献上しています。

初代 桝屋庄五郎作 「草刈童子」

光格天皇より拝領 「十六葉八重表菊紋印」
有職御人形司
十二世 伊東久重

役職
伝統文化保存協会
理事長
表千家不審菴
理事
国際京都学協会
理事
金剛能楽堂財団
顧問
大聖寺文化・護友会
副会長
京都市文化観光資源保護財団
評議員
略歴
昭和19年
有職御人形司 伊東家の長男として生まれる。同志社大学在学中より人形制作を始める。
昭和53年
十二世 伊東久重を継承。
昭和59年
和光にて個展。(以後、現在まで13回)
昭和60年
日本政府の要請により科学万博・日本歴史館にて「伊東久重 御所人形の世界」展。
昭和60年
高島屋京都店美術画廊にて個展。(以後、現在まで11回)
平成12年
京都にて「十二世 伊東久重 御所人形の世界」展。(京都新聞主催)
平成12年
静岡にて「十二世 伊東久重 御所人形の世界」展。(静岡朝日テレビ主催)
平成16年
オーストリア・ウィーンにおいて「The World of the 12th HISASHIGE ITOH’s GOSHO-NINGYO」展を開催。
平成17年
福岡にて「十二世 伊東久重 御所人形の世界」展。(北九州市主催)
平成21年
佐川美術館にて「宮廷の雅 伊東久重 御所人形の世界」展。(読売新聞社主催)
平成22年
北村美術館四君子苑にて「十二世 伊東久重展」。(同23、24年)
平成26年
高島屋京都店美術画廊にて「十二世 伊東久重 ・ 建一展」を開催。
平成30年
静岡県駿河平に「有職御人形司十二世伊東久重美術館」開館。
平成30年
高島屋京都店グランドホールにて「有職御人形司 十二世伊東久重の世界」展。(朝日新聞社・京都新聞主催)
平成30年
スペイン・マドリードにおいて「MUÑECAS DE PALACIO DEL MAESTROHISASHIGE ITO XII」を開催。
平成30年
日本橋高島屋S.C.本館8階ホールにて「有職御人形司 十二世伊東久重の世界」展。(朝日新聞社主催)
略歴
昭和46年
有職御人形司 伊東家の長男として京都に生まれる。幼名・建一。高校生の頃より制作の基本、「粗彫り」を始め、大学卒業後、父である 十二世 久重のもと本格的に御所人形師の道に入る。
平成17年
和光にて最初の作品を発表。
平成21年
佐川美術館にて開催の「宮廷の雅 伊東久重 御所人形の世界」に特別出品。
平成22年
和光にて初個展「伊東建一 御所人形展」 を開催。
平成24年
箱根やまぼうしにて 「伊東建一 御所人形の世界」を開催。
平成26年
高島屋京都店美術画廊にて「十二世 伊東久重・建一展」を開催。
平成26年
箱根やまぼうしにて 「伊東建一 御所人形の世界」を開催。
平成26年
JR名古屋高島屋美術画廊にて「伊東建一 御所人形展」を開催。
平成27年
同志社女子大学非常勤講師に就任。
平成27年
福屋八丁堀本店美術画廊にて「伊東建一御所人形展」を開催。
平成28年
箱根やまぼうしにて「日本の工芸 その伝統と未来」を開催。
平成30年
有職御人形司十二世伊東久重美術館にて「伊東建一作品展」を開催。
令和元年
久重十三世嗣として後嗣名「庄五郎」を襲名。
令和元年
高島屋大阪店美術画廊にて「御所人形師 伊東庄五郎展」を開催。
令和4年
高島屋京都店美術画廊にて「御所人形師 伊東庄五郎展」を開催。
令和4年
有職御人形司十二世伊東久重美術館にて「久重十三世嗣 伊東庄五郎展」を開催。